「赤血球が少ない」と
指摘を受けたら…?
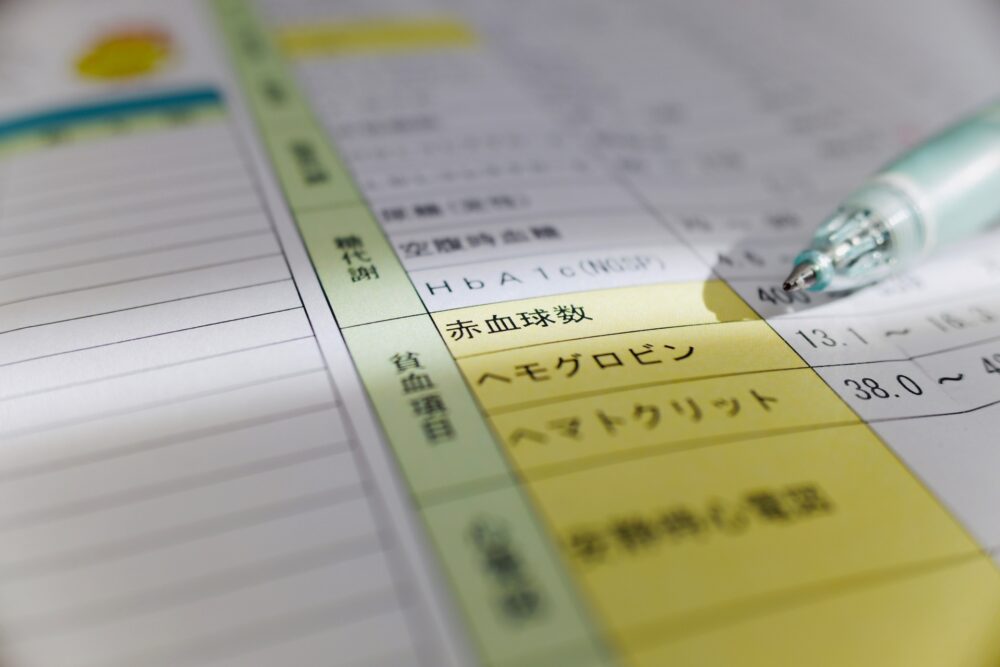 赤血球が少ない状態は「貧血」と呼ばれ、血液中の赤血球やヘモグロビンの量が正常範囲を下回ることを指します。
赤血球が少ない状態は「貧血」と呼ばれ、血液中の赤血球やヘモグロビンの量が正常範囲を下回ることを指します。
赤血球は体内の酸素を運搬する重要な細胞であり、全身の組織に酸素を供給します。赤血球はヘモグロビンを含み、ヘモグロビンに酸素が結合することで全身に酸素が供給されます。ヘモグロビン濃度が低い場合、赤血球の数が正常でも、酸素の運搬能力が不足することがあります。このため、貧血は単に赤血球の数が少ないだけでなく、ヘモグロビンの不足によっても引き起こされるのです。
貧血は、男性ではヘモグロビン濃度が13g/dL未満、女性では12g/dL未満とされています。貧血が発生すると、体に必要な酸素が十分に供給されなくなり、さまざまな症状が現れます。
「赤血球が少ない」ときに
見られる症状
「赤血球が少ない」ときに
考えられる病気
鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は、最も一般的な貧血の一種で、体内の鉄分が不足することによって引き起こされます。鉄はヘモグロビンの合成に不可欠な成分であり、その不足は酸素の運搬能力を低下させます。原因は多岐にわたり、不適切な食事や偏食が一因となることが多いですが、潰瘍や腫瘍といった消化管からの出血や、妊娠・授乳中の鉄需要の増加が原因となることもあります。
症状としては、初期段階では疲労感や息切れ、肌の蒼白が見られ、進行するとめまいや集中力の低下、心拍数の増加などが現れます。女性や妊婦に多く見られる病気です。
検査では血液検査が行われ、ヘモグロビン濃度や赤血球数、鉄分濃度、フェリチン(体内の鉄の貯蔵状態を示す指標)を測定します。
鉄欠乏が確認された場合、治療は主に鉄剤の投与や食事の見直しとなります。重症の場合は、出血源の特定と治療が必要になることもあります。鉄分が豊富な食事を心掛けることで予防が可能ですが、症状がある場合は早めにご相談ください。
再生不良性貧血
再生不良性貧血は、骨髄での造血障害によって、正常な血液細胞(赤血球、白血球、血小板)が十分に作れなくなる病気です。自己免疫反応、薬剤、化学物質、放射線、感染症など原因は多岐にわたりますが、90%以上が特発性(原因不明)とされています。
症状は全身の倦怠感、感染症の頻発、出血傾向(皮下出血や鼻出血など)などが見られます。特に血小板の減少が顕著な場合、出血のリスクが高まります。赤血球の減少による貧血症状も現れ、息切れやめまいを引き起こすことがあります。
診断には、骨髄穿刺が用いられ、骨髄の細胞の状態を評価します。また、血液検査では赤血球、白血球、血小板の数を確認し、各種の血液成分が正常に生成されているかを調べます。治療方法には、免疫抑制療法や骨髄移植が含まれますが、治療の選択肢は病期(ステージ)によって異なります。
溶血性貧血
溶血性貧血は、赤血球が通常よりも早く破壊されることによって発生する貧血です。正常な赤血球は約120日間生存しますが、何らかの原因でこれが短縮されると、骨髄は新たな赤血球を十分に生成できず(消費に対して生産が追い付かない)、貧血状態に陥ります。溶血性貧血の原因には、自己免疫によるものや、遺伝性球状赤血球症といった遺伝的要因、感染症、特定の薬剤反応などが考えられます。
主な症状としては、貧血に伴う疲労感や息切れのほか、赤血球が破壊されることによって生じる黄疸、褐色尿、脾腫(脾臓の腫れ)が見られます。特に、自己免疫性溶血性貧血では、体内の免疫系が自己の赤血球を攻撃してしまうことが問題となります。
診断には血液検査が行われ、赤血球の数、ビリルビン値(赤血球の破壊に伴って増加する)、網赤血球数(新しい赤血球の生成を示す指標)などが評価されます。治療は原因によって異なりますが、免疫抑制療法や輸血、場合によっては脾臓の摘出が必要です。高度な治療が必要な場合には連携する医療機関をご紹介いたします。
巨赤芽球性貧血
(ビタミンB12欠乏性貧血、葉酸欠乏性貧血など)
巨赤芽球性貧血は、ビタミンB12や葉酸の欠乏により、赤血球が正常に成熟できなくなることで発生します。赤芽球と呼ばれる未成熟な細胞のまま、血球の分化が進まないため、細胞が異常に巨大化し、正常な赤血球が不足します。食事からの栄養素の吸収不良、特に胃の手術後や腸の病気、またはビタミンB12の吸収を妨げる自己免疫疾患(悪性貧血)が原因とされます。
症状としては、貧血による疲労感や息切れ、また神経症状(しびれや運動障害)も見られることがあります。これらの神経症状は、ビタミンB12が神経機能に重要であるため、欠乏が進行すると発生します。
診断には、血液検査が行われ、赤血球のサイズや数、ビタミンB12や葉酸の濃度を測定します。また、骨髄検査が必要なこともあります。治療は、欠乏しているビタミンB12や葉酸の補充が必要で、注射を選択します。骨髄検査が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。
骨髄異形成症候群
骨髄異形成症候群は、骨髄での血液細胞の形成が異常になる病気です。赤血球、白血球、血小板のいずれにも障害が出る可能性があります。貧血だけでなく、白血球も血小板数も低下することがあります。原因は未だ完全には解明されていませんが、抗がん剤治療や放射線被曝、遺伝的要因などがリスク要因として知られています。症状は、貧血による疲労感や息切れ、感染症の頻発、皮膚のあざや出血などが見られます。
診断には、骨髄穿刺が行われ、骨髄の細胞の状態を評価します。血液検査では、赤血球や白血球、血小板の数を測定し、形態異常が確認されることもあります。病期(IPSS-Rによるリスク)により治療法が異なります、輸血療法のみの支持療法となる場合もあれば、アザシチジン治療や骨髄移植が選択されることもあります。高度な検査や治療が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。
再生不良性貧血
赤血球だけでなく、白血球や出血を止める役割を持つ血小板が減少する病気です。赤血球の減少により貧血症状が現れるだけでなく、白血球の減少によって感染しやすくなり、発熱や咳などの症状が出ます。さらに、血小板の減少により皮膚に赤紫の小さな出血点(点状出血)や、紫色の斑点(紫斑)、大きなあざ(斑状出血)が見られることがあります。
年間100万人に8人ほどの発症率で、10〜20歳代や70〜80歳代に多く見られます。原因はほとんどの場合不明ですが、遺伝的要因や薬剤が原因となる場合もあります。骨髄にある造血幹細胞の減少が主な要因と考えられています。
治療は病期(ステージ)によりますが、輸血や免疫抑制剤、ホルモン治療が行われます。造血幹細胞移植が選択されることもあります。高度な検査や治療が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。
「赤血球が少ない」に関するよくある質問
赤血球が少なくなる原因は何ですか?
赤血球が少なくなる原因としては、上記に記載したような病気の他、ビタミンB12や葉酸の不足なども考えられます。
食事で赤血球を増やすことは出来ますか?
骨髄に問題がない場合には、適切な栄養を摂取することで赤血球を増やすことが可能です。
具体的には以下のような栄養素が重要です。
- 鉄分(赤身の肉、ほうれん草)
- ビタミンB12(卵、乳製品、魚)
- 葉酸(緑黄色野菜、豆類)
赤血球が少ないとどのような合併症が考えられますか?
赤血球が少ない状態が長期間続くと、以下のような合併症が起こる可能性があります。
- 重度の疲労、無気力
- 心不全
赤血球が少ないのは一時的なものですか?それとも慢性的な問題ですか?
赤血球が少ない原因によって一時的な場合もあれば、慢性的な場合もあります。例えば、急な出血や一時的な栄養不足が原因の場合は、適切な治療を受ければ短期間で回復することがあります。しかし、慢性疾患や遺伝的要因によるものは長期間にわたり治療が必要なことが多いです。
赤血球が少ない状態でも運動していいですか?
軽度の貧血の場合は、軽い運動が推奨されることもありますが、重度の貧血がある場合は運動を控えるべきです。運動をすると、酸素供給が不足して息切れや疲労が悪化することがあるため、まずは医師までご相談ください。
赤血球が少ないことに気づかずに放置するとどうなりますか?
軽度の場合はあまり症状がないこともありますが、重度の貧血を放置すると以下のような深刻な問題が生じることがあります。
- 心臓や脳に十分な酸素が供給されず、心不全や脳の機能低下を引き起こすリスクが高まる
赤血球が少ないと頭痛が起こるのはなぜですか?
赤血球が少ないと、酸素が十分に供給されないため、脳への酸素供給が不足します。これにより、頭痛やめまい、集中力の低下といった症状が引き起こされることがあります。特に、立ち上がったときに頭がふらつくことが多いです。








